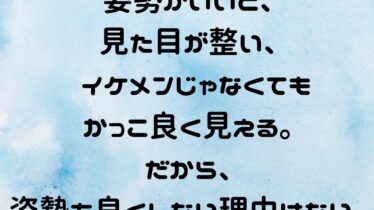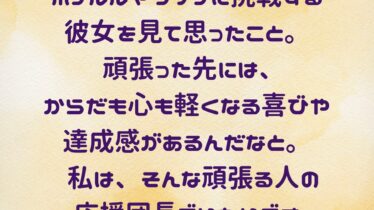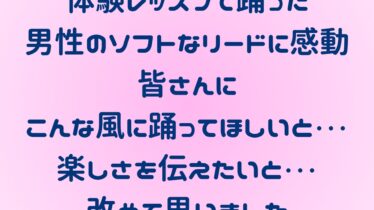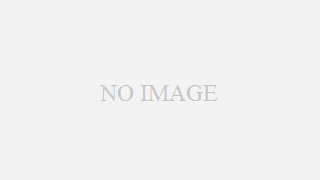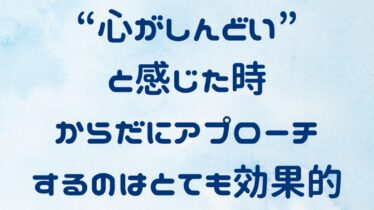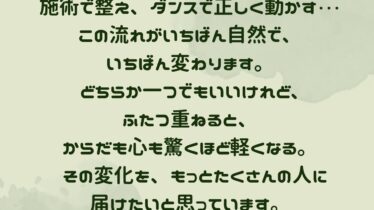 ストレッチ
ストレッチ 【ストレッチとダンスは“ひとつの流れ”で最強になる】
【ストレッチとダンスは“ひとつの流れ”で最強になる】
ストレッチとダンスは、一見別物に見えます。
でも私たちのスタジオでは、どちらも「からだと心を整える」同じ目的につながると考えています。
もちろん、どちらか一方を選んでも、からだの動かしやすさや姿勢、気持ちの変化などの効果はしっかりあります。
ただ、両方を取り入れると、その効果はさらに大きく、相乗効果が生まれます。
ストレッチで土台を整えると、ダンスで正しい動き方が分かる。
ダンスで動くことでからだの隅々が使われ、またストレッチの効果が深まる。
私たちは、強制はしません。選ぶのはあなた自身。
でも、両方取り入れた人が得られる軽やかさと心地よさは、やはり最強です。
だからこそ、その変化を、もっとたくさんの人に届けたいと思います。