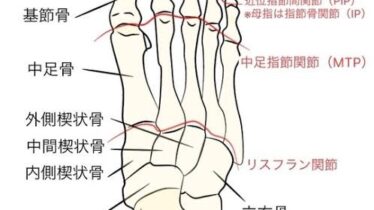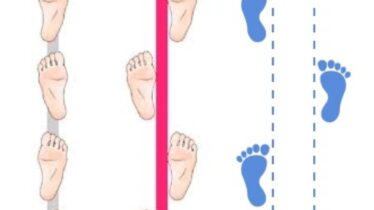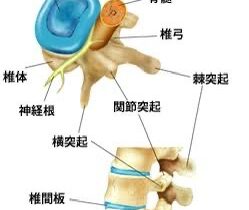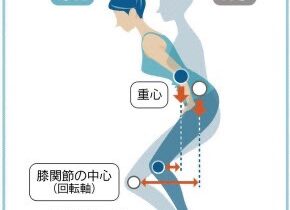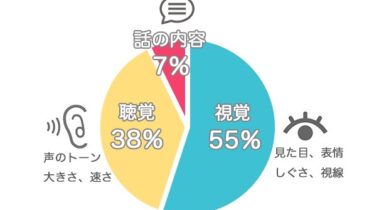未分類
未分類
子どもの頃の1年はもっと長かったような気がしますが、歳を重ねるごとに時間の流れを早く感じます。
今年最後のLINEとなりました。
毎年ティチャーとスタジオの大掃除をして1年を締めくくっていますが、今年は床がシューズの滑り止めの影響でまだらに黒くなっていたのを、キレイにすることができてご機嫌で年が越せます。気になっていたから本当に嬉しいんです。来年はいいことしかない予感がするほどです。
皆さんどんな1年でしたか?
いろんなことがあった1年だったと思いますが、締めくくりの今日は、“よく頑張った一年だってね”って、自分で自分を労わる1日にしたものですね。
いつも格別のご愛顧を賜り、心よりお礼申し上げます。
皆さんのお陰で無事に営業することができました。
ありがとうございました。
来年もStudio Connectをご愛顧いただけますよう、よろしくお願い致します。
良いお年をお迎えください。